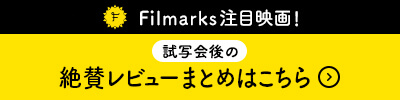INTERVIEW
スペシャルインタビュー


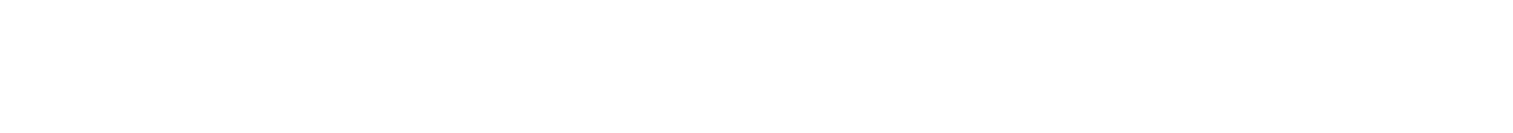
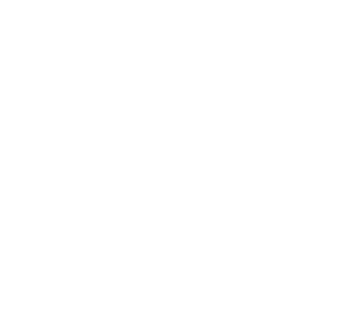


話し合いながら
4年かけて書いた脚本

Q:皆さんの出会いはどのような感じだったのですか?
- 阿部:
- 藤井くんとはよく映画の話をしていたけど、「そのうちふたりで映画を作れたらいいね」というところから始まったんだよね。
- 藤井:
- 継続的に会って「こういう映画が好きだ」と語り合っていたけど、その時に出たアイディアが『デイアンドナイト』の原形ですね。
- 山田:
- 僕が最初に会ったのは、新宿の狭い居酒屋だったんじゃないかな。
- 藤井:
- そうそう、ふたりで考えた想いを書いた一枚の紙が出来上がった頃で…。
- 山田:
- その時は、まだメモみたいな感じでしたよね。僕はそれまで映画のプロデュースをやったことがなかったけど、興味だけは昔からあったんです。ただ、プロデューサーとしての能力は何もないから、一緒に作ってゆく中で学ぶ形になってしまう。でも、影響力とか、人を集めることなら絶対に協力できると思って「プロデューサーとして入れてくれないか?」とお願いしました。ここがチャンスだなと。
Q:脚本開発はどのように進めていったのでしょうか?
- 藤井:
- 2013年に書き始めたので、決定稿まで4年かかったことになりますね。
- 阿部:
- 最初は、中国人の話だったこともあったよね。
- 藤井:
- そうそう、確か17稿くらいでは引きこもりのニートが主役だった。
- 阿部:
- 役者としては(脚本開発から)参加することで、キャスティングが行われる前の段階でどういうことが行われているのかを知れただけでも、とてもメリットがありました。作品に対する責任感も生まれたし、引いた眼で映画を作る感覚も持てた。作り手のひとりとして今までとは違う意識を持ちましたね。
- 山田:
- みんなで脚本に対する意見を出し合うんだけど、そこで書いたものはプロジェクターで壁に投影して、全員で見るんです。演じる役者がその場にいるので、映し出された台詞をお互いに演じてみる。そうすることで、台詞の違和感を取り払っていけたことが良かったと思います。
- 藤井:
- 明石役の阿部さんはそこにいるので、それ以外全部の役を山田さんがその場で芝居するんですよ。芝居をしてみて、つかえるような箇所があれば、戻ってやり直す。それを何度も何度も繰り返しましたね。
- 山田:
- 書いている台詞ではなくて、生きた言葉にしなければならない。それって、登場人物の気持ちになって発しないとわからないものなんです。例えば、演じている時に「これ、どこで息継ぎすればいいんだ!?」というような台詞が時々台本上であったりする。息継ぎだったり、人それぞれのリズムって絶対的なところがあるんですよ。台詞をちゃんと生きた言葉にするためには、やって良かった。
- 阿部:
- 迷いまくったからこそ「これではない」ということは、確かにあったね。
- 藤井:
- そうやって時間をかけて28稿くらいまで書き直した脚本の中で、最初からブレていないのは、主人公が<明石>という名前のキャラクターであることと、“昼と夜”や“善と悪”に対する二面性というテーマくらいですね。
- 阿部:
- 僕らは表現者の集まりだとも思っていて、オリジナル脚本にこだわったというよりも「生み出したものを映像にしたい!」という気持ちが自然に湧き出てきたのだと感じます。
- 山田:
- 映画を作りたければ、僕はオリジナルでやるべきだと思うんです。確かに、アイディアをストーリーにしなければならない0→1の大変さはありますが、原作ものになると、原作者がいて、出版社がいて、ファンもいる。じゃあ「どのくらい変えていいのか?」「変えるべきではないのか?」ということも考えたら、意外とオリジナルを作った方が大変ではないのかも知れないですね。
地元の人々の協力で
現場が動いた

- 藤井:
- 秋田県での撮影は11月だったのですが、例年より寒い時期にぶつかってしまって。
- 山田:
- この時期は雪が降らないと言われていたのに、どわっと降ってきて。みんなで雪かきをしまくった。
- 藤井:
- 山田さんが率先してやるので、休んでいるスタッフも休めないという…。
- 山田:
- 現場に入ると、案外することがないんですよ。
- 阿部:
- 地元の方々にとっては、映画の現場自体が珍しいだけではなくて、2〜3分のシーンを撮るのにも時間がかかるということが新鮮だったようでしたね。みなさんにも僕らの熱が伝わっていると感じました。
- 山田:
- 1ヶ月の間、3つの町で撮影したけど、それぞれの町で自然と実行委員会や炊き出し隊ができたんです。それで有り難いことに毎回、炊きたての<あきたこまち>が出てくる。こんな贅沢な現場は、今まで経験したことがないです。
人間の善悪への問いかけ———
Q:(宣伝用のチラシに書いてある)「愛する家族の命が奪われたとしたら、あなたはどうするだろうか」という言葉が印象的でした。
- 山田:
- これは、かなり初期段階の言葉だよね。
- 藤井:
- 初めて会った時に、山田さんが言ったことですよね。
- 山田:
- その時とった行動を他人から善だとか悪だとかジャッジされるのは「どう思いますか?」ということなんです。その人の感情ではなく、行動だけでジャッジすることを「どう思いますか?」と。
- 阿部:
- 法律で裁かれるとしても、感情は考慮されると思うんです。でも、基本的には行動を見られますよね。
- 藤井:
- それが問いかけられるような内容になっていればいい、と僕は考えていました。愛する人を失った時、その感情や怒りを殺意に変える人だけではないと思うんです。「失ったものに対してどう折り合いを付けますか?」ということは、自分の中の<隣人愛>と似ているのかも知れません。最初から描きたかったことのひとつに<血の繋がらない家族の愛>というものがあって、善と悪の曖昧さと同じように、家族関係の曖昧さということもキーワードでした。
- 阿部:
- <血の繋がらない家族の愛>というのは、物語の中で関係性を問いやすい設定でしたよね。血が繋がっているからこそ当たり前だと思っていたことが、「本当の家族じゃない」とわかった瞬間に、突然当たり前でなくなる。そう描くことで、より考えるきっかけになるのではないかと思いました。もしかするとこの<血の繋がり>という関係性というものは、時代性なのではなくて、我々人間がずっと問われてきたことなのかも知れないですね。

Q:それでは「善と悪はどこからやってくるのか?」というテーマについてはどうですか?
- 藤井:
- 僕は“どこから”という部分が気になっていて。この映画で描いたように、誰かから見た悪は、誰かから見た善であったりもするので「外的要因で人は善悪を決めるのだろうか?」ということに対して、自分の感情の中でも折り合いがついていなかったんですね。
- 阿部:
- やはり「何をもって自分の中で正義とするか?」ということについては意識しましたよね。正しいか正しくないのかは自分で判断するしかない。それを法律に当てはめる人もいれば、自分のルールに当てはめる人もいます。戦争映画を観ていると、片方の側からしか描いていないようなことがあって「そんなことあるかよ!」とずっと思っていたので、そういう要素がこの映画に入ればいいなと思っていました。
- 藤井:
- そう、だから、昼に見える顔と夜に見える顔の違いについては、最初の段階から書いていたよね。
Q:見方が変わると見え方も変わってくるということですね。
- 藤井:
- それが一番やりたかったことで、例えば、世の中で一方的に報道されているようなニュースを見ても「果たしてそうなのかな?」と僕は思ってしまうんです。だから視点を変えれば、この映画の中で明石が守ろうとしたものや、彼なりの正義というものが見えてくるはずなんです。
答えを出したいのではなく、
話がしたい

Q:昨今、“わかりやすさ”や“共感”というものを映画に求める傾向が一部でありますが、その点について皆さんはどのようにお考えですか?
- 山田:
- 例えば、この映画は架空の人物の架空の出来事なので、共感できなかった観客がいたとしても、それは当然だと思います。一生経験しないような出来事もたくさん描かれているので、もしかすると自分の人生には当てはめられないかもしれない。でも僕は、共感することよりも考えることの方が大事だと思っているので。
- 阿部:
- 共感するかしないかということは、僕もよく考えますね。人は「いかに自分事になるのか?」ということでしか、その人のことを考えられない。自分と違うことに対しては違和感があって、受け入れ難いものなのだとは思います。ただ、最近の世の中の風潮として、とてもクリーンなものを求めている傾向がありますよね。そうじゃないのが現実なはずなのに、臭いものに蓋をされているように感じることもあります。
- 山田:
- だから、共感って素敵なものでもあるけれど、同時に無責任なものでもある。
- 藤井:
- 共感値の高い映画というのは、確かにあると思います。それこそ、青春映画のように、観客が今まで経験してきたこととリンクすることは、共感値を高くさせる。だから逆に「こんな世界ってある?」という覗き穴的な面白い映画を僕らは目指したところがあります。
- 山田:
- もし1回観てわからなければ、2回観ればいい。人それぞれに読解力があるので、それを下げて、下げて、下げてゆくと、もともと読み取り能力の高い人からすると「何て説明的な映画なんだ」となる。だったら、平均値みたいなことは考えず、僕らなりのいい塩梅で映画を作ればいい。この映画は、はっきりと説明してあるから僕はわかりやすいと思っています。
- 阿部:
- 想像するということが、だんだんと減っているのかも知れませんね。「これはこういうものだ」と、みんな決めつけるけど「その理由って何?」と聞くと、特に理由がなかったりする。
- 藤井:
- これは個人の好みだと思うのですが、僕は「こうだよ」という映画よりも「こうなのかな?」という映画が好きなんです。つまり、観客に問いかけることをやりたかった。そこも初稿からブレていないところです。
- 山田:
- 僕らはこの映画で答えを出したいのではなくて、話がしたいんです。「僕らは疑問に思いましたが、みなさんはどう思いますか?」と。
(TEXT:松崎健夫)